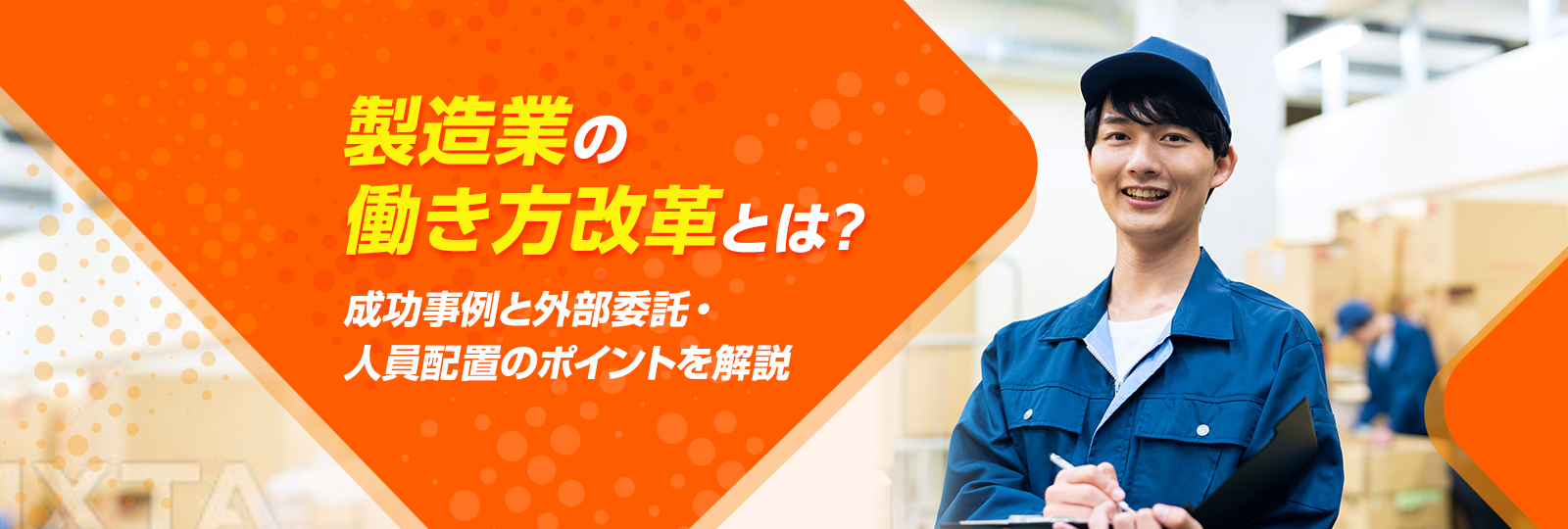
2019年から順次施行されている「働き方改革」。とりわけ製造業においては、背景に人手不足や長時間労働、デジタル化の遅れといった課題があり、生産性向上と就業環境の改善の両立が求められています。
本記事では、製造業における働き方改革の現状と課題を整理しつつ、外部委託・請負を通した改革のポイントについて解説します。
働き方改革とは、厚生労働省が推進する「働く人々が個々の事情に応じて多様で柔軟な働き方を選択できる社会の実現」を目的とした取り組みです。
2019年4月以降、順次施行されている「働き方改革関連法」では、以下の三本柱を基軸として法整備が進められています。
これらの制度整備の背景には、日本が直面する深刻な課題があります。少子高齢化による労働人口の減少、長時間労働の慢性化、雇用形態による賃金格差の拡大、さらには育児・介護との両立など働き方のニーズの多様化に対応するため、包括的な法改正が実施されています。

製造業は、働き方改革の実現において高いハードルを抱える業界と言えます。以下では、製造業特有の主要な課題について詳しく見ていきましょう。
製造業では、労働時間の適正化に向けた課題を抱える企業も少なくありません。
まず、シフト制・交代制を採用する企業では、拘束時間の長期化が慢性的な問題となっています。さらに、生産計画の急な変更、設備トラブルなどの突発的事象が日常的に発生することから時間外労働が常態化しやすく、長時間労働の是正に向けた取り組みが思うように進まないケースも散見されます。
この問題をさらに深刻化させているのが人手不足です。十分な人員を確保できないことで、残業や休日出勤が常態化し、さらには人材育成に必要なリソースも確保できないという悪循環に陥る企業も少なくありません。
製造業の働き方改革における最大の課題の一つが、慢性的な労働力不足です。特に若年層の就業者数は減少傾向にあり、継続的な人材確保は年々困難になっています。
経済産業省「2025年版ものづくり白書」によれば製造業に従事する34歳以下の若年層は、2014年から2024年の10年間で約13万人減少しています。一方、65歳以上の高齢就業者は2018~19年には94万人まで増加したものの、現在は88万人と緩やかに減少しています。
労働力不足が継続すれば、多能工化に向けた教育機会の減少や、ベテラン社員の退職による技能継承の阻害など、将来の生産力・競争力の維持に深刻な影響を与える可能性があります。
製造業の人手不足問題に対するより具体的な対策や、外部委託を活用した成功事例について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

製造業の人材不足対策とは?外部委託・請負の活用法と成功事例を紹介
現在、日本の製造業界全体で人手不足が深刻化しています。本記事では、人手不足問題の現状分析から、具体的な対策、外部委託・請負の活用法、成功事例まで詳しく解説します。
省人化による業務効率化と労働時間削減を実現するためには、デジタル技術の積極的な活用が欠かせません。
経済産業省「2025年版ものづくり白書」のデータによると、調査対象となった製造業企業の約8割が何らかの形でデジタル技術を活用した業務改善に取り組んでおり、特に「製造」「生産管理」「事務処理」分野での導入が進んでいます。
しかし、デジタル技術の活用状況には企業規模による明確な格差が存在します。大企業ほど活用率が高い一方で、中小企業では導入コストの負担や現場のITリテラシー不足といった課題により、対応が後手に回っているのが現状です。
こうしたデジタル化の遅れは単なる効率化の問題にとどまらず、働きやすい環境整備の遅れにも直結しています。例えば、ロボットの導入により肉体的負担の軽減を図ることで、男性だけでなく、女性や高齢者など多様な人材の活用機会の促進も実現できます。

製造業において働き方改革を進めるにあたっては、自社の現状を正確に把握し、多角的なアプローチを講じる必要があります。ここでは、製造業における代表的な取り組みを紹介します。
製造業において常態化しやすい長時間労働を是正するため、労働時間の見える化や、生産計画の見直し、設備導入などに取り組む企業が増えています。また、労働時間の上限規制に対応した労働時間管理の徹底により、従業員の意識を高めることも有効です。
育児や介護との両立を支援する柔軟な制度の導入は、従業員の定着率向上やエンゲージメント強化に寄与します。時差出勤や短時間勤務、フレックスタイム制度など、ライフステージに応じた働き方の選択肢を広げることで、企業の魅力向上にもつながります。
働き方改革の本質は、単に労働時間を減らすことではなく、限られた時間で最大の成果を生み出す体制づくりにあります。多能工化による人材の柔軟な活用や改善活動の促進などを通じて、生産性向上と働きやすさの両立を目指しましょう。
生産性向上のための具体的な手法や、工場改善の成功事例については、以下の記事で詳しく解説しています。
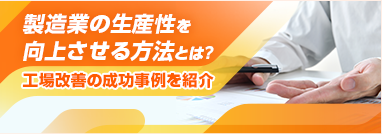
製造業の生産性を向上させる方法とは?工場改善の成功事例を紹介
生産性とは、生産過程で投入される要素(原材料や設備、労働力など)に対して、どれだけの成果物(製品)を生み出せたかを示す割合を指します。本記事では、生産性を向上させる方法をご紹介しています。
限られたリソースの中で成果を最大化するには、外部委託や請負の活用も有効な選択肢のひとつです。それにより、社内人材は本来のコア業務に専念でき、生産性の向上と時間外労働削減が可能になります。さらに、外部の専門性の高い人材を取り入れることで、現場改善や工程の最適化の推進などの効果も期待できます。

製造業において働き方改革を推進するうえで、外部委託や請負の活用は重要な選択肢のひとつです。ここからは、製造業の働き方改革における外部委託や請負のメリットについて、詳しく解説します。
そもそも製造請負契約とは何か、その基本から最新のトレンドまで詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

製造請負契約とは?製造業界のトレンドと展望
製造請負契約とは、製造業の一部または全体の生産プロセスを外部業者に委託する契約のことです。本記事では、製造請負契約の基本的な定義から最新のトレンドまで詳しく解説します。
外部委託・請負の最大の利点は、一定の専門性を持つ人材を、採用活動や教育にかかる時間・コストを大幅に削減して活用できることです。委託・請負契約であれば、必要に応じた柔軟な人材活用が可能となります。
またそれらの人材は、すでに専門的な教育を受け、スキルや実務経験を有しているケースが多く、企業側での初期教育はほぼ不要です。これにより、教育コストの削減が可能になるだけでなく、客観的な視点で改善活動を活発化するため、業務の効率化も期待できます。
さらに、ノンコア業務を外部に委託することで、社内の人的リソースをコア業務に集中させることができます。この結果、組織としての生産性が大幅に改善されます。さらに、正社員の業務負荷軽減により時間外労働の削減も実現でき、社内の働き方改革の推進に直接的に寄与します。
制度面での重要なメリットとして、法定福利費が不要であることが挙げられます。業務委託の受託者は企業との雇用関係がないため、社会保険料等の企業負担が発生せず、固定的な人件費負担を大幅に削減できます。
さらに、業務委託契約は短期間や案件単位での契約が可能なため、業務の繁閑に応じた人員調整が実現できます。これにより人件費の無駄を削減し、余剰予算を正社員の処遇改善や採用強化に活用することが可能になります。
製造業における働き方改革を成功させるには、適切な人員配置が不可欠です。しかし、外部委託や請負の導入にあたっては、いくつかのポイントと注意点を押さえておくことが重要です。
請負や業務委託契約では、労働者との雇用関係と指揮命令関係が、いずれも受託業者(請負業者)に帰属します。注文主(発注企業)は業務の成果物に対して対価を支払いますが、労働者個人に対する直接的な指示や管理は行いません。請負や業務委託契約を結んでいる労働者に対し、注文主が直接指揮命令した場合、「偽装請負」と判断される可能性があります。
偽装請負と判断された場合、労働基準監督署から指導を受けることとなり、場合によっては懲役または罰金などの罰則が科されることもあります。
どのように指揮命令の有無を判断するのかについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

製造請負契約の指揮命令に注意!範囲や指揮命令者を知り偽装請負を防ぐ
製造請負契約では、正しく理解せず指揮命令を行った場合に偽装請負となり、労働者派遣法違反とみなされることがあります。本記事では製造請負契約の指揮命令について解説します。
偽装請負のガイドラインである「37号告示」についてはこちらをご参照ください。
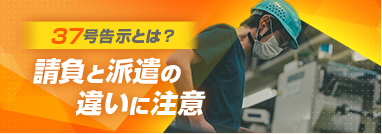
37号告示とは?請負と派遣の違いに注意
37号告示とは、請負契約と派遣契約の違いを明確に区別し「偽装請負」の防止を目的とするガイドラインです。どのように指揮命令の有無を判断するのかについて具体的な事例を紹介しています。

現在、製造業でも働き方改革に取り組み、成果を挙げている企業が増えています。ここでは、労働環境の改善と生産性の両立を実現した具体例をご紹介します。
株式会社ミスズ工業では、時間外労働の削減を目指し、1分単位での労働時間のデータ管理を徹底しました。その結果、2015年当時は月平均17.2時間だった時間外労働が、2020年度には月平均5時間まで大幅に削減されました。また、有給休暇取得率の向上にも注力し、年間10日の取得を目標として、個人ごとの取得状況を管理することで、2020年度には平均9.6日を達成しました。
経営層から明確な数値目標が示され、現状を可視化することで、従業員の意識を高めることに成功した事例です。
ライオンパワー株式会社では、従来の一人一作業の体制から、部門全員が複数の機械を操作できる「多能工化」を成功させました。まず1部門で中核的な社員が他の社員に技能を伝承し、半年程度で部門内のほとんどの装置を全員が扱えるように。その後、すべての部門で多能工化が実現されました。
この取り組みにより、5年間で月平均残業時間は約60時間から30時間へと半減。業務の属人化を防ぎ、柔軟な人員配置が可能となったことで、働き方改革の一環として高い成果を上げています。
株式会社平山が支援した食品製造メーカG社では、シーズン需要の変動を受けやすい商品を扱っており、生産量の増減に応じて契約社員の募集・解約を繰り返すことで、労務への負担が課題となっていました。
この問題を解決するため、外部の正社員で構成された請負チームを投入し、コンサルタントによる生産性向上指導を実施。その結果、生産量の変動に柔軟に対応できる体制が実現しました。労務コストの削減により働き方改革を実現しただけでなく、余計な人件費や労務費をも大幅に削減することに成功した事例です。
製造業における働き方改革は、単なる「労働時間の短縮」や「制度の整備」だけではなく、組織全体の生産性や競争力を左右する課題へと変化しています。今後は特に、以下の3つの視点が重要になります。
製造業においてもIoTやAIの導入により、現場の自動化が進められています。特に、デジタル技術導入にやや遅れを取っている中小企業にとっては、こうした技術を導入することが働き方改革の大きな推進力となるでしょう。
人材不足が深刻化する製造業において、多様な人材の活用は不可欠です。高齢者、女性、外国人労働者といった多様な背景を持つ人材の受け入れを積極的に進めるとともに、短時間勤務制度やフレックスタイム制など、柔軟な雇用形態の選択肢を充実させることが重要です。
限られた社内人材を最大限活用するため、外部リソースの戦略的活用がますます重要になっています。この取り組みにより、組織全体の生産性が向上するだけでなく、正社員はより付加価値の高い業務に専念でき、結果として企業全体の競争力向上を実現できます。

製造業における働き方改革には、多角的かつ実践的な取り組みが求められます。なかでも、外部委託や請負の戦略的な活用は、現場の人手不足といった課題を解決しながら、労働環境の改善や生産性向上といった改革の目標達成にも貢献できる有効な手段のひとつです。
ただし、その効果を最大限に引き出すためには、信頼できる委託業者の選定や、法令遵守を前提とした適正な運用体制の構築が不可欠です。
株式会社平山では、製造業に特化した請負契約の導入支援を行い、コンプライアンスを重視した業務管理体制の整備をサポートしています。平山の請負事業にご関心をお持ちの方は、ぜひ以下のリンクからお問い合わせください。